中学3年生(新高校1年生)の春休みの過ごし方②(修正再掲)
- 家庭教師のMIC
- 2023年3月19日
- 読了時間: 3分
先週掲載した「中学3年生(新高校1年生)の春休みの過ごし方」の続きです。
受験後から高校入学までのこの時期は、今しかできないことをしてみた方がよい、と私は思っています。学習量をゼロにするのは問題ですが、受験が終わって疲れている時に休息をとらないでいると、高校に入ってから息切れしてしまうことになるからです(最近は高校を中退する生徒が少なくありません)。
また、勉強ばかりしていると、勉強の目的が受験だけになってしまい、合格後には学習した内容をすっかり忘れてしまったり、あるいは学校のブランドで人間の価値が決まると勘違いしてしまうこともあるでしょう。
さらに社会体験が少なければ、学習内容を社会生活で応用できなくなってしまいかねません。あくまでも学校での学習とは自らが社会生活を送る手段であって、人生の一部に過ぎないのです。
ですので、休んだり遊んだりすることも大切です。
その「休んだり遊んだり」の中で触れるのを忘れていたことの1つが、読書です。
普段読書をしていない生徒は、この機会に読書に挑戦してみてはどうでしょうか。
現代社会の制度はその多くが文字で多くが成り立っています(規則や法律、契約)。ですので普段から文章に慣れておけば、多くの知識を得ることができ、社会生活が楽になります。それだけでなく、好きな本に出会えれば、読書は新たな趣味にもなり、人生の楽しみも増えます。
では、普段読書をしない生徒は、どのような本を読めばよいのでしょうか。
導入としては、自分の好きなことに関わる本がよいでしょう。野球でもゲームでもユーチューバーでも構いません。とりあえず「本」というものを手に取って、「読み切った」という成功体験が大切です。
また、ドラマや映画などを観て、すでに筋書きを知っている本は、かなり読みやすいです。それだけでなく、原作と映像のストーリーの違いが分かって面白いです。
その上で、では具体的にどのような本がよいのかを紹介してくれ、と言われると、私はかなり困ってしまいます。というのも、私が現在読んでいる本は、中学生向けではないからです。そこでプロの知識をお借りします。
どんな本を読んだらよいのか全く見当がつかない生徒は、国語の教科書で紹介されている本の中から、自分の趣味にあう本をまず読んでみて下さい。そこでは、各学年に適切な本を紹介しています。
文章読解が苦手な生徒なら、中学1年生の国語の教科書で紹介されているものを読んでみたらよいでしょう(こういう各学年向けの本を書いたり、それを選び分けて紹介するのは、まさにプロの仕事だと感心します)。
なお、現代社会で好まれる速読や多読が、「正しい」読書方法とは限りません。「思考の仕方もまた多様」で書きましたが、ゆっくりじっくり読むことは、深く広く物事を考える上で大切なことです。特に詩は味わう時間が大切です。
読書以外にも、例えば映画鑑賞、博物館・美術館の訪問、旅行など、普段中々できないことに挑戦してみるのもよいと思います。
一見学習に関係ないように思えることが、実は学習に深く関わっていることも、非常に多いです。また、人生を歩む上では、学校の主要教科が立脚する論理性・科学性以外の事柄、すなわち感情や情緒が非常に大切になってきます。
ですので、学校の教科だけに捉われず、様々な物事に触れてみる期間にしてみて下さい。
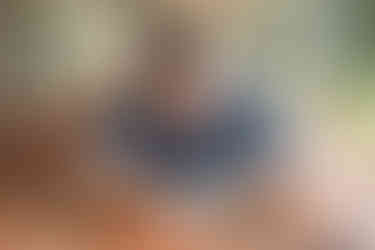
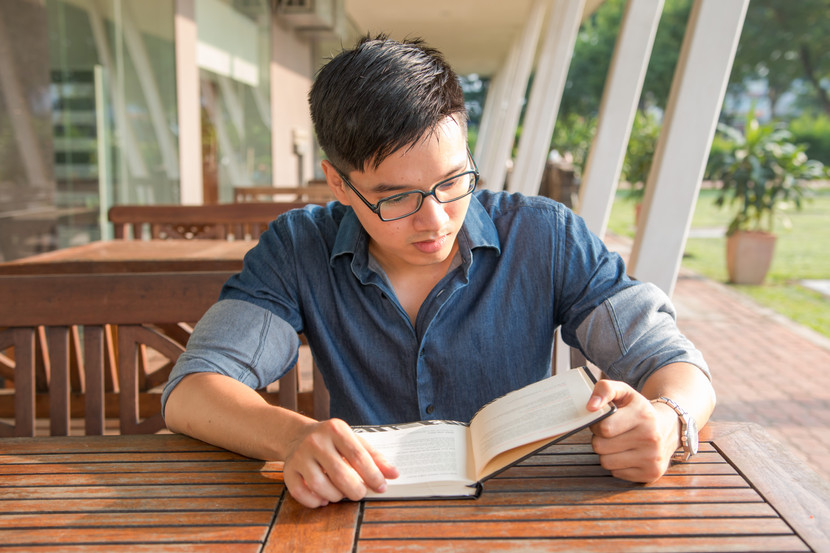


コメント