イチゼロ思考も多様な考えにつながる(再掲)
- 家庭教師のMIC
- 6月30日
- 読了時間: 2分
イチゼロ思考は良くない、という言い方がされます。物事をイチかゼロかで考えるな、と。
つまり、イチゼロ思考は多様性を否定する、頑固な考え方だということです。
ここで、指をつかって数を数える時を想定してみましょう。
普段私たちが使っている10進法で考えると、右手だけで数えられる数は、0~5までです。
ところが、イチゼロしかない2進法で考えると、右手だけで0~31まで数えられます。
つまり、イチゼロを繰り返す2進法は、使い方によっては10進法よりも様々な数を表すことができるわけです。
ここでイチゼロ思考について振り返ってみましょう。
「良い」か「悪い」や「好き」か「嫌い」だけで思考を停止してしまうと、多様な考え方は生まれません。
しかし、「好き」「嫌い」で始めても、「好き」or「嫌い」→「とても」or「あまり」→「それでも」or「さらに」という選択肢を重ねていくと、様々な表現ができます。
こうしたことを書いたのは、自身の感覚と言葉の秩序にズレがある、自閉症スペクトラム障害の児童生徒は、中々自分の思ったことや感じたことを言葉にできないことを念頭においてのことです。
ところがこうした児童生徒も、2進法の選択肢を重ねていくと、自分の感覚を表現することができます。もしかすると、0~31に感じていることを、0~5に表現するように求められているために、表現できないのかもしれません。
こうした2進法を利用した表現の訓練は、定型発達者(いわゆる健常者)にも応用できます。
例えば、外国語の単語を覚える際や、意見を述べる際に、まずポジティブなイメージかネガティブなイメージか、に分けてみましょう。
すると、存外単語を覚えやすくなったり、意見を述べやすくなったりします。
その上で、ポジティブの中のどれか、ネガティブの中のどれか、と細分化していくと、覚えられる単語が増えたり、述べる意見が深くなったりすることもあります。
つまり、"Yes, and/but", "No, and/but"と考えるだけで、表現する幅は、相当に広がるのです。
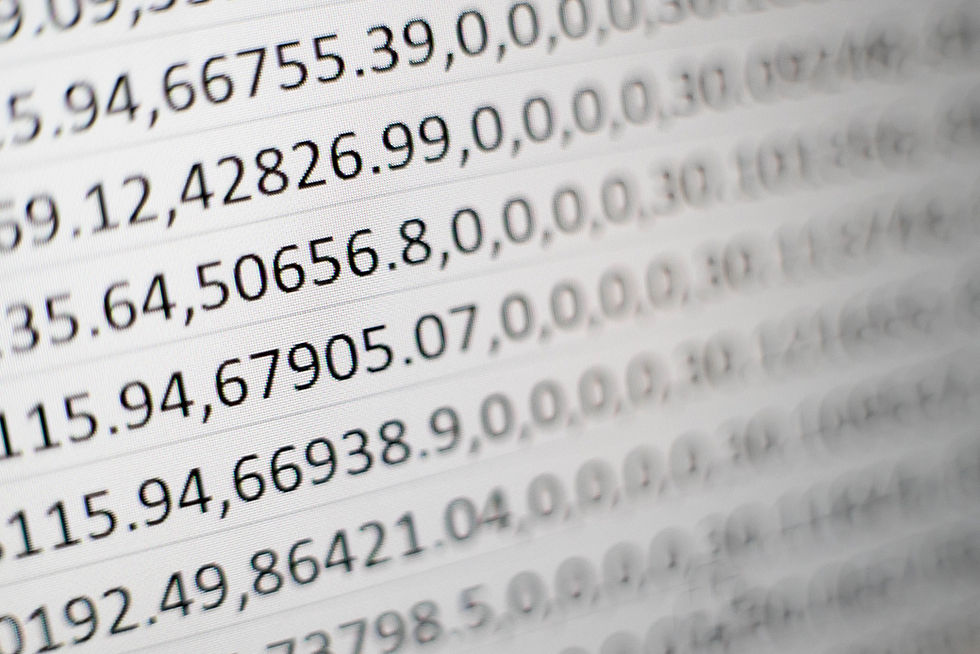


コメント