高校古文はどうしてつまらないか③
- 家庭教師のMIC
- 2023年4月23日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年5月20日
高校古文はどうしてつまらないか② の続きです。
古文で文法を学ぶ重要性がわかり文法事項を一つ一つ覚えてきて、さらに古文の文章の書き方が現代語のような作法に基づいていない理由がわかり、ある程度文章を読めるようになっても、また面倒なものが出てきます。
歌の中の枕詞だとか縁詞だとか掛詞だとか。
何ですかそれは。それが分かったからといって、これからの人生に何の役に立つのでしょう。実際に、現代社会でそういった詩歌の表現技法を使って生きている人は、それほどいないでしょう。
それにも関わらず、こういう表現技法が使われていると、上手い歌だと評価され、「これ試験に出すからな、しっかり覚えろよ!」と言われます。
でも、でもそんな表現技法があったから上手いといわれても、自分はなにも感動しませんし、入試で出るからって言われるから覚える、というのが多くの高校生の実感でしょう。
感動どころか脅迫です。
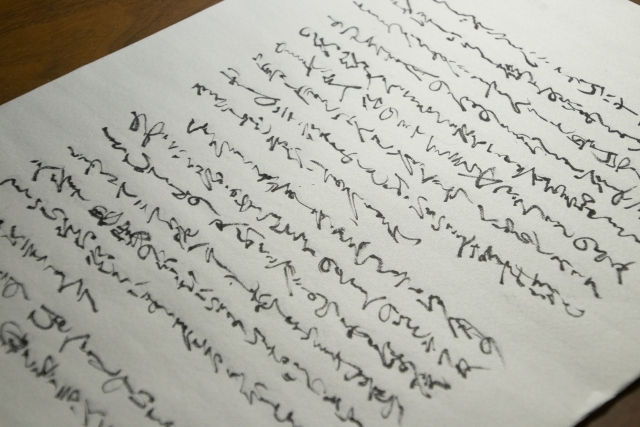
ところが、その「入試で得点になる」ことが実はこうした詩歌の表現技法の理解には大切です。
詩歌の表現技法に「入試で得点になる」ということに似た効果が、おそらく古代からあったとは考えられないでしょうか。
近代以前の日本には、試験によって公務員を登用する制度がありませんでした。つまり、権力者が個々人の能力を図って人材登用をする中立的な物差しが無かったわけです。
そうなると、詩歌のそうした表現技法ができるかどうかも、その人の能力を測る手段であったと考えられます。すると、詩歌の表現技法は実は読み手の地位や権力に直結するものであったのではないでしょうか。
すなわち、ワタシばっちり枕詞覚えてますし、縁詞や掛詞のコンボ技繰り出せます。こんな才能ある私は、しっかりとお仕えしてお役に立てますよ、というアピールになっていたりとか、はたまた「縁詞とか掛詞使った私って凄いだろ」と思って、チラッと異性に色目を使ったりしていたのかもしれません。
そう考えながら古文を読み返してみてください。
(『更級日記』なんかは、純粋な『源氏物語』腐女子であった著者が、世俗の欲にまみれて、天皇家の乳母になって一生安泰な生活を送ってやろうという野心を持つものの、それに敗れてしまい、過去の純粋な腐女子時代を懐かしんで書いたものです。)
詩歌の表現技法、というよりも文学は、「上手い」とか「美しい」とかそうしたことばかりが強調されて教えられます。しかし、人間のあり方なぞそんなに変わるものではありません。
カネと色と権力。残念ながら、どんなに人格者を装っていてもほとんどの人々は世俗的欲求を満たすために芸術を利用しています(芸術を自己の使命と感じている人は、自己の理想と現実的な存在の矛盾に耐えられず、生き長らえません)。
詩歌とは、世俗的欲求を露骨にせずに、「雅に」求める方法の1つであることが多かったと思います。ですから、そうした「雅な」表現技法の背景にあるヨダレを垂らすような世俗的欲求を想像してみて下さい。古文に登場する人物に親近感がわきます。
大体昔の世界がそんなに美しかったのならば、誰も出家しません。というよりも、昔の方が人間関係にはドロドロしたものが多く、しかも昔ならば、そんなドロドロが自分の生命を脅かすからこそ出家してお寺に入ったわけです。
なにせ平安時代なんかも宮使いできなければ、生命の補償など一切ない時代でした。だれか間違えて「不安時代」と書いていましたが、座布団あげたいです。点数はあげられませんけれど。



コメント